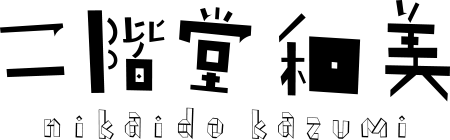つれづれにか vol.22
掲載:QUATTRO PRESS vol.68 / PARCO-CITY FLYER 2007 December
 映画を人と一緒に見にいくのは実は苦手だ。実は、というのはそれでも一緒に行くこともしばしばあるということなのだが、見ているときの横の気配云々は映画への集中力で消せたとしても、上映終了後、とりあえずなにか口をきかないといけないのがなんとも気まずい。「トイレ行ってくるわ」的な現実的な事を話すのも興ざめだし、「どうだった?」なんて言い合うのはもっと野暮だ。特に良かった時。それは寝起きにも似ていて、夢の余韻がもったいなくてしばらく布団の中から出たくないのと同じような、非常にプライベートな内面世界への旅であり、同じ映画を見ても自分の内面のどこと共鳴したかというのは人それぞれ千差万別と思う。それを話すのには、かなりの時間と筋道を要する。ではとりあえず何を話すか?
映画を人と一緒に見にいくのは実は苦手だ。実は、というのはそれでも一緒に行くこともしばしばあるということなのだが、見ているときの横の気配云々は映画への集中力で消せたとしても、上映終了後、とりあえずなにか口をきかないといけないのがなんとも気まずい。「トイレ行ってくるわ」的な現実的な事を話すのも興ざめだし、「どうだった?」なんて言い合うのはもっと野暮だ。特に良かった時。それは寝起きにも似ていて、夢の余韻がもったいなくてしばらく布団の中から出たくないのと同じような、非常にプライベートな内面世界への旅であり、同じ映画を見ても自分の内面のどこと共鳴したかというのは人それぞれ千差万別と思う。それを話すのには、かなりの時間と筋道を要する。ではとりあえず何を話すか?
先日、母も見たいということで連れだって見に行った『エディット・ピアフ 愛の讃歌』。2時間20分という長編ながら、隣の気配を気にする隙もなく引きずり込まれる映画だった。直後の感想として言及すべきは女優さんのすごさ。この女優さんのしゃべる声がピアフとよく似ており、彼女自身が歌っているところとピアフ本人の録音が挿入される部分との区別がほとんどつかないほどだった。この女優さんマリオン・コティヤールさんは歌のことがわかっている人とお見受けした。恐れ入ると共に、なんて事だ。女優ってどういうことだ。女優さんがこんなに歌えてしまったら歌手なんて全く出る幕がないじゃないか。とおぞましいほどに感嘆した。吹き替えという違和感をまったく感じさせなかった演技ということだから、その細部にわたる研究のほどはますますすごい!ということになる。その姿勢に多大なる敬意を抱いた。吹き替えと聞くと一瞬「なーんだ」と思うところもあるが、いやいやなるほど、ここまでの演技でつないでくださったらそれはそれは非常に誠実なやり方であると納得、ファンとしては最も嬉しい形である。実在の人物をモデルとした音楽映画やドラマがたいていは白けるのに対し、この映画からは女優業というプロフェッショナルな意識と技を魅せられ、とても気持ちのよい後味であった。
描かれたピアフ本人からの触発は言うまでもない。